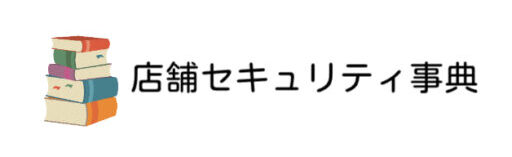住宅や店舗・事務所の防犯対策というと、ドアや鍵に目が行きがちですが、実は「窓」からの侵入が非常に多いことをご存じでしょうか。
警察庁の統計でも、一戸建てでは侵入窃盗の約半数以上が窓から行われているとされており、共同住宅でも油断は禁物です。ちょっとした鍵のかけ忘れや、外から見えにくい立地、足場になるものの存在など、侵入者にとって好都合な条件は意外と身近に潜んでいます。
本記事では、狙われやすい窓の特徴と、今すぐ始められる具体的な防犯対策をわかりやすく紹介します。
窓からの侵入被害が多い?
警察庁のデータなどによれば、住宅や店舗・事務所における侵入窃盗のなかで、窓からの侵入が非常に多くを占めています。たとえば、一戸建て住宅では全侵入窃盗のうち 約50%以上が窓を突破口としており、共同住宅でも階数によらず窓からの被害が無視できません。
「窓」は見た目には無防備に見えることが多く、「ちょっと開けっぱなし」「鍵が古い・簡単に壊せそうなもの」「外から見られにくい・足場が近い」などの条件がそろうと、侵入者にとって格好のターゲットになります。
そこで、まずは「どんな窓が狙われやすいか」を把握し、それに応じた対策を行うことが、防犯強化への第一歩です。
参考サイト:警視庁 住まいる防犯110番
狙われやすい窓の特徴
以下のような窓は、侵入者から狙われやすい傾向があります。当てはまる項目はないか、店舗・事務所の窓をチェックしてみてください。
- 引き違い窓(スライド式)…クレセント錠が使われていることが多く、鍵の構造が単純でこじ開けられるリスクが高い。
- 低階層の窓…1階や地面に近い掃き出し窓など。侵入が容易である。
- 道路や人通りの少ない裏手…外からの視線を遮るもの(塀・植木・物置など)があると「見られにくさ」が増し、侵入の時間的余裕を与えてしまう。
- ベランダや外部の足場が近い窓…隣家のベランダ、エアコンの室外機、雨どいや配管などを伝って2階・3階に上がれるような足場があると、想定よりも侵入が容易になる。
- 掃き出し窓、大きなガラス面の窓…人が通れる大きさ・開口のある窓は侵入のしやすさが高く、侵入者が隠れて行動できるリスクも出てくる。
- 鍵のかけ忘れ・古い鍵・簡単に壊せそうな鍵…うっかり鍵をかけていなかったり、クレセント錠だけで補助錠がなかったりするものなど。
これらをすべて対策できれば、侵入されにくい窓が見えてくるはずです。
窓の防犯対策
新入されやすい窓が分かったら、対策を実施しましょう。住宅・店舗・事務所の用途・予算・立地によって組み合わせるとより効果的です。以下に、ご自身でできる対策から、外部へ委託する方法まで、幅広くご紹介しましょう。
| 対策 | 主なメリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 防犯フィルムを貼る | ガラスを割られにくくし、破片の飛散を抑える。比較的安価で、自分で設置可能なタイプがある。 | 窓ガラスの全面に貼らないと効果が十分でない。結露などでフィルムが剥がれることもあり。賃貸では貼る前に許可が必要。 |
| 補助錠(追加錠)の設置 | 窓のこじ開けに対する抵抗力が上がる。設置費用も低め。 | 頻繁に開け閉めする窓だと使い勝手が悪くなること、取り付け・操作を忘れると意味が薄くなる。賃貸の契約・管理者への確認が必要。 |
| 防犯センサー・アラーム | 窓が開いた時/ガラスが揺れた時に音や通知が出る。寝ているときや外出時などに安心感が得られる。 | 誤作動(風・小動物など)を防ぐための配置や感度調整が必要。電源・メンテナンスも考慮。コストは機能によって幅がある。 |
| 防犯カメラの設置 | 犯罪の抑止力がある。発生後の証拠として映像を残せる。見えるところにあるだけで心理的な威嚇になる。 | 見た目を損なう/配線工事が必要な場合は工事コストがかかる。プライバシーへの配慮や設置許可も必要な場合あり。ダミーと判断されてしまうと効果が薄い。 |
| 防犯ガラスへの交換 | 通常のガラスより割れにくく、破壊への耐性が高い。割れてもガラス片が散らばりにくい。 | コストが高い。既存サッシとの相性・外観への影響・施工業者選びが重要。賃貸物件では許可が必要。 |
| 内窓(二重窓)設置 | 防犯性が上がるだけでなく、断熱性・防音性も改善できる。複数のガラスを越える必要があるため、侵入しにくくなる。 | 開閉の手間が増えること・掃除の手間が増えること・費用がかかること。設置可能な窓枠かどうか、建物の構造との相性をチェック。 |
| 面格子の設置 | 物理的な障壁になるので、ガラスが割れても直接入りにくくなる。比較的確実性が高い。 | 見た目・採光・視界が悪くなることがある。固定式・可動式で防犯性能に差が出る。デザインと機能のバランスを考える必要あり。 |
| シャッターや雨戸の利用 | 窓を完全に遮断できるので、侵入リスクをかなり下げられる。視覚的な抑止力も強い。 | 価格が高め。設置・開閉の手間や日常の使い勝手(開けることを忘れてしまう・重さなど)に注意。特に電動のものはメンテナンスも必要となる。 |
| センサーライトを設置する | 人が近づくと明るくなることで「見られているかもしれない」という意識を与えられ、侵入をためらわせる効果あり。比較的低コストである。 | 設置位置や角度が悪いと効果が限定的になる。夜間の誤点灯による近隣への迷惑や電池、電源管理も考える。 |
複数の要素を組みわせほど、防犯対策の精度は高まります。コストや準備期間などを加味しながら、適切な対策を講じましょう。
まとめ
窓は侵入者にとって格好のターゲットとなりやすいため、早めの対策が欠かせません。狙われやすい窓の特徴を把握したうえで、防犯フィルムや補助錠、センサーや防犯カメラなど複数の対策を組み合わせることで、侵入リスクを大幅に下げられます。
また、面格子や防犯ガラスなど本格的な設備も有効ですが、賃貸や共有住宅では管理者の許可が必要です。重要なのは「簡単に侵入できない」「人目につきやすい」環境をつくること。日常的な点検・管理を習慣化し、窓まわりの防犯性を高めましょう。