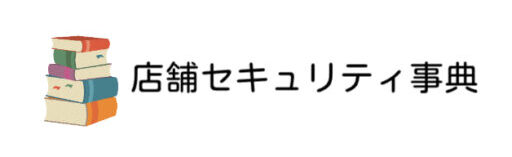企業における情報セキュリティの脅威は、外部からのサイバー攻撃だけではありません。実は、従業員や退職者など内部関係者による情報の不正持ち出しや改ざんといった「内部不正」が、組織に深刻な損害を与えるケースが増えています。
内部不正は一度発生すると顧客情報や知的財産の流出につながり、信頼失墜や経済的損失を招くだけでなく、事業継続にも影響しかねません。そのため、経営層は起きる前提で備える意識を持ち、制度・技術・文化の三面から防止策を講じることが不可欠です。
本記事では、内部不正が起きる原因や対策のポイントを解説します。リスクに備える方法を知りたい経営者の方は、参考にしてみてください。
内部不正とは?
「内部不正」とは、現職従業員・アルバイト・契約社員のみならず、退職者なども含めて、組織の関係者が故意・過失を問わず、機密性の高い情報を不正に扱う行為を指します。具体的には、情報の不正持ち出し、漏えい、消去・改ざん、外部への不正アクセスなどが含まれます。
独立行政法人IPAにおいても、組織内部者の不正による顧客情報や製品情報などの漏えいは事業の根幹を揺るがし、内部不正が発生するリスクや効果的な対策の検討は、組織にとって重要であると定義しています。対岸の火事と安心せず、経営者は不正が起こらない体制づくりが必要不可欠です。
参考ページ:独立行政法人IPA 情報処理推進機構 組織における内部不正防止ガイドライン
発生しやすい状況と原因
内部不正が発生する状況にはいくつかの共通点があり、人的要因と技術的要因の両面から原因を整理できます。ここでは、それぞれの特徴と原因について解説します。
人的要因
内部不正の発生要因の一つに、人的な要因が挙げられます。
- 動機(モチベーション)…金銭目的、待遇・評価への不満、キャリア上の不安などが内部不正の動機となることがある
- 機会…アクセス権限が過剰・管理が不十分・監視体制が弱いなど、不正を働く余地がある環境
- 正当化…この程度なら問題ない」「みんなやっている」「会社が自分を軽視している」といった心理が、不正を自分で正当化してしまう
これらは「不正のトライアングル」と呼ばれるモデルで、動機・機会・正当化の3つが揃うと不正の発生確率が高まります。企業にとっては、これらの発生を防ぐことが非常に重要です。
技術的要因
人的なものだけでなく、技術的な面も発生要因に関係しています。代表的なものは、次の通りです。
- アクセス権限の管理不足…業務上の必要性を超えた権限を与えている、または退職者・異動者のアカウント処理が遅れているなど
- ログの取得・監視体制の未整備…どの操作が誰によって行われたかを記録・追跡できないと、不正を後から確認することが難しく、抑止力が弱まってしまう
- 外部記録媒体・クラウドへのデータ持ち出しの制御不足…USBメモリ、個人クラウドストレージ、ファイルアップロード機能などが制限・監視されていないと、情報が簡単に持ち出されてしまう可能性がある
- 誤操作・過失…意図しなくても誤って情報を外部に公開したり、誤ってファイルを共有したりするケースも多く報告されており、このようなミスを防ぐ仕組みがないことがリスクとなる
防止の基本原則と対策のポイント
内部不正を完全にゼロにすることは難しいですが、「不正の三要素(動機・機会・正当化)」を抑える仕組みと組織文化をつくることが効果的です。ここでは、具体的な対策のポイントについて解説します。
犯行のハードルを上げる
不正を行う物理的・技術的なハードルを上げることで、実行を困難にし、未然に防ぐ狙いがあります。
たとえばアクセス権限の細分化(職務に応じた最小権限の付与)したり、業務端末・外部記録媒体の使用制限(USBメモリや私物端末の禁止)したりします。
また、入退室管理や監視カメラの設置で物理的な制限を加えるのも有効です。内部不正の機会の低減につながり、動機があっても行動に移しにくくなります。
犯行を見つかりやすくする
監査体制と可視化を強化することで、「発覚リスクが高い」と感じさせるのが目的です。具体策としては、次のようなものが挙げられます。
- 操作ログ・監査ログの取得と保全
- ファイルアクセスやデータ転送の監視・アラート通知
- 定期的な内部監査・ログレビューの実施
不正を行ったとしても「必ず発見されてしまう」と従業全員に認識させることで、抑止効果を発揮します。
不満を減らす環境づくり
不正に手を染めたくなるのは、組織に対して何らかの不満が隠れているケースも。従業員を公平に評価したり、意見を言いやすい職場風土を醸成したりすることが、結果として内部不正の発生を防ぎます。
定期的なストレスチェックや相談窓口を設けることで、「会社から不当に扱われる」と感じたときに、相談できる環境を整えることも大切です。システムの構築はもちろん、従業員の働きやすい環境を整えることも忘れないようにしましょう。
不正行為を正当化させない
内部不正を防ぐには、そもそも従業員が不正行為を「やむを得ない」「仕方がない」と正当化できない環境を整えることが重要です。そのためには、組織全体で倫理観や規範意識を共有し、不正に対する心理的抵抗感を高める取り組みが欠かせません。
具体的には、情報倫理やコンプライアンスに関する教育を定期的に行い、最新の事例やリスクを周知することで意識を継続的に向上させます。また、情報セキュリティポリシーを明文化し、全従業員から誓約書を取得することで、責任と自覚を明確にさせます。
不正が発覚した際の処分基準や懲戒規定を具体的に示し、社内に広く周知することも有効です。こうした仕組みにより、従業員が不正を起こす余地をなくし、倫理に反する行為を文化的に排除する企業風土を形成できます。
まとめ
内部不正は、従業員の不満や環境要因、管理体制の甘さなど複数の要素が重なることで発生します。完全なゼロは難しいものの、発生要因を抑える仕組みを整え、従業員が不正に手を染めにくい環境をつくることは可能です。
最小権限の徹底やログ監視、持ち出し制御などの技術的対策に加え、従業員教育や相談体制の整備、公平な評価制度など文化的・人的な対策も欠かせません。経営層自らが関与し、全社的な取組として継続的に実施することが、内部不正防止の鍵となります。