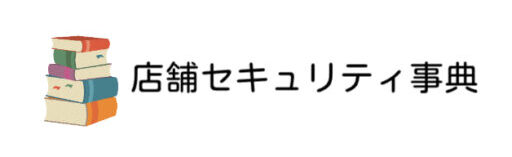デジタル化が進む中、サイバー攻撃や情報漏えい、不正アクセスなどの脅威は企業規模を問わず増加しています。特に中小企業はセキュリティ体制が脆弱な場合も多く、標的になりやすいのが現状です。
万が一被害が発生すれば、調査や復旧費用だけでなく、顧客への賠償、信用失墜、営業停止による損失といった多大な負担が発生します。セキュリティ対策だけでリスクをゼロにするのは困難なため、被害発生後の経済的損失をカバーする「サイバーリスク保険」への注目が高まっています。
本記事では、サイバー保険の概要や補償内容、選び方のポイントを解説します。
サイバーリスク保険とは?
近年、ビジネス環境におけるデジタル化の進展、テレワークやクラウド利用の普及、IoT(モノのインターネット)やキャッシュレス決済といった新しい技術の導入が急速に進んでいます。その一方で、サイバー攻撃や情報漏えい、不正アクセス、ランサムウェアなどの脅威がより巧妙かつ多発するようになっており、企業にとっての被害リスクが格段に高まっています。セキュリティ対策を講じていたとしても、未知の攻撃や人的ミス、システムの脆弱性など、完全にリスクをゼロにすることは難しいのが現実です。こうした背景から、被害が発生した際の損害を軽減するための“保険”=サイバーリスク保険の必要性が、ますます重要視されています。
サイバーリスク保険(またはサイバー保険)は、情報漏えい、ネットワークの停止やシステム障害、顧客データの流出やそれに伴う賠償責任、さらには営業利益の損失など、サイバー事故・攻撃によって発生する様々な損害を補償する保険です。被害をカバーする補償範囲や条件は保険会社や契約内容によって異なりますが、事故の対応費用・調査費・賠償責任・営業停止による損失などが対象となるケースが一般的です。
あらゆる業種にサイバー保険が必要な理由
「大きな企業ではないから、特に保険は必要ない」と考える店舗経営者もいるかもしれません。ここでは、サイバー保険が必要な理由について解説します。
サイバーリスクの拡大と被害の深刻さ
サイバー攻撃の対象となるのは、国・自治体・金融機関だけではありません。小売業・飲食業・製造業など、多様な業種がサイバー攻撃を受ける可能性があります。
もし攻撃によって被害を受けると、情報漏えい・データ改ざん・サービス停止・サイバー攻撃によるシステム障害など、多岐にわたり大きなリスクが発生します。復旧のための費用が発生するのはもちろん、信用失墜や営業損失、訴訟対応等間接的な損害も重くのしかかります。小規模企業でも会員情報の漏えいやウェブサイトの不正アクセスによって、数千万円規模の被害が生じるケースも珍しくありません。
セキュリティ対策だけでは被害を防げない
被害を受けないためには、ファイアウォール・ウイルス対策ソフト・アクセス制限などの対策は必須です。しかし、人的エラー(メール誤送信、USBメモリ紛失など)、ソフトウェア更新の遅れ、未知のゼロデイ脆弱性など、完全に封じることのできない経路が常に存在します。
また、テレワークなどオフィス外で仕事をする機会が増加したことにより、自宅や公共のWi-Fi環境が十分なセキュリティ設定でないことを狙われるケースも増えています。こうした対策の抜けや、万一起きたときを想定しておくことが、保険加入の意義です。
損害発生時の対応コストを抑えるため
事故が発生した際には、被害調査、原因の究明、再発防止策の策定、法律相談、顧客・取引先対応など、多様な対応が必要になります。これらは迅速に対応しなければ被害がさらに大きくなりかねず、また、体制が整っていない中小企業では対応準備が十分でないことも多く、初期対応の遅れが大損害を招くことがあります。
サイバーリスク保険に加入しておくことで、こうした対応費用の補償が受けられるほか、初期対応の専門業者紹介などサポートが付帯している商品もあります。これにより、企業自身の負担と時間的ロスを軽減できるのが大きなメリットです。
主な補償内容と保険がカバーする範囲
サイバーリスク保険の契約を検討する際、以下のような補償内容と補償対象の範囲をよく確認する必要があります。
| 補償内容 | 具体的な対象 | 注意点 |
|---|---|---|
| 損害賠償責任 | 顧客や取引先からの情報漏えいに基づく損害賠償請求、法律上の責任、裁判や訴訟の弁護士費用など | 請求可能な相手先・範囲(国内・国外)、免責額や限度額、過失責任の扱いをチェックする |
| 事故対応・調査費用 | 原因調査、被害範囲の特定、データ復旧、復旧作業、セキュリティ専門家への連絡、原因対策など | 対応の速さによって被害の広がりが変わるので、補償開始までの時間やサポート体制が重要。オプション扱いのケースもありうる |
| 営業・利益損失 | システム停止・ネットワーク障害等による売上減少、営業活動不能期間の損失 | 補償対象となる停止原因の範囲・期間・証明方法が制限されることが多い |
| 広報・顧客対応費用 | 顧客通知、謝罪広告、コールセンター設置など | 補償対象になるかどうか、どの程度の費用までが認められるかは保険による |
| 予防・再発防止対策費用 | セキュリティ診断、脆弱性対策、システム強化など | 加入前の状態での要件が厳しい保険もあるので、契約前に確認が不可欠 |
また、情報漏えい保険とサイバー保険とで補償範囲に違いがあります。後者のほうがより幅広い事故・対応に対応していることが多いです。
サイバーリスク保険を選ぶポイント
サイバーリスク保険を選ぶ際は、費用や条件を十分に確認することが重要です。まず保険料は、企業の売上高や業種、従業員数、扱う情報の機密性、現行のセキュリティ対策状況などによって左右され、リスクが高いほど高額になります。
次に、補償範囲と免責額を把握することも大切です。営業損失や利益の逸失といった間接的損害は上限が低めだったり、自己負担が大きめに設定されている場合があります。
加えて、事故発生後の調査・復旧・広報支援など、サポート体制の充実度も被害拡大防止に直結します。故意や不正行為、戦争・テロなどは補償外となるケースが多く、ランサムウェアの身代金支払いが対象外の保険もあります。さらに、定期的なセキュリティ診断や従業員教育を契約継続の条件とする保険もあるため、自社の体制整備と合わせて慎重に選ぶことが求められます。
まとめ
サイバー保険は、情報漏えいやシステム障害などの被害に伴う費用・賠償・営業損失を幅広く補償してくれる心強い備えです。保険を選ぶ際は、保険料や補償範囲、免責額、事故時のサポート体制を慎重に比較することが大切です。また、故意や不正行為、戦争・テロ行為など補償対象外となるケースもあるため、契約前に条件をよく確認する必要があります。
保険に加入するだけでなく、日頃からのセキュリティ強化や従業員教育も並行して行うことで、被害の発生確率と影響を最小限に抑えられます。経営を守るため、今こそ備えを見直しましょう。