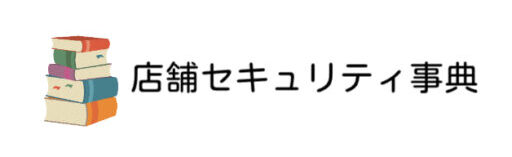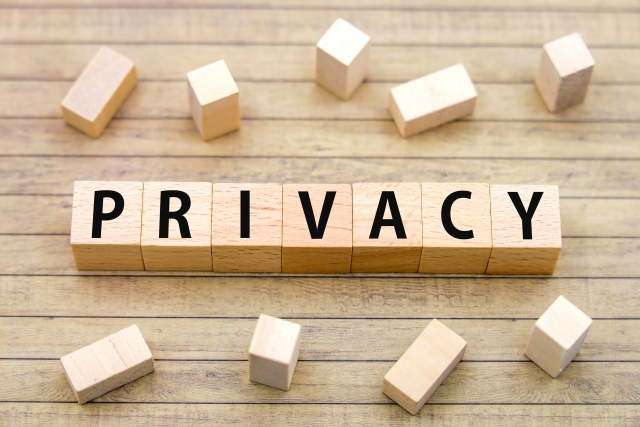情報漏えいは、企業の信用失墜や損害賠償など、経営に深刻な打撃を与えるリスク要因です。とくに近年はクラウド活用やリモートワークの普及により、社外で情報を取り扱う機会が増えたことで、従来よりも漏えいリスクが高まっています。
しかも情報漏えいの多くは、悪意ある外部攻撃だけでなく、従業員の不注意や操作ミスといった「ヒューマンエラー」が原因です。そのため、単にセキュリティ製品を導入するだけでなく、従業員の行動ルールや教育、アクセス管理、データ監視などを含めた多層的な対策が欠かせません。
本記事では、企業が実施すべき情報漏えい防止策を解説します。自店舗でしっかりと対策ができているか、確認してみてください。
顧客情報漏えいのリスクとは?
顧客情報が漏洩してしまうと、店舗にとってさまざまなリスクが発生します。ここでは、代表的なものを2点ご紹介しましょう。
ブランドと社会的信頼の失墜
情報漏えい事故が発生すると、その事実はニュースやSNSを通じて一気に拡散し、多くの人々の目に触れます。結果として「情報管理がずさんな企業」「セキュリティ意識が低い企業」といった負のイメージが定着しやすくなり、企業全体のブランド価値や社会的信用を大きく損なう恐れがあります。
一度失われた信頼は、短期間で回復できるものではなく、長期的な信用低下を招く要因となります。その結果、顧客離れや取引先からの契約解除など、事業継続に直結する深刻な影響を及ぼしかねません。
損害賠償や訴訟による経済的損失
情報漏えいにより顧客や取引先が実害を受けた場合、企業には損害賠償責任が生じる可能性があります。たとえば、顧客データの流出によってSNSでの風評被害が広がったり、取引先の営業活動やサービス提供が一時停止に追い込まれたりした場合、その損失補填を求められるケースがあります。
過去には、賠償額が数億円規模にのぼり、経営基盤を揺るがす事態に発展した事例もあります。こうした金銭的負担は突発的かつ甚大であり、場合によっては企業の存続を脅かすリスクとなり得ます。
情報漏えいを防止するポイントは?
情報漏えいは、経営者の意識だけでは防止できません。ここでは、具体的なポイントを解説します。
情報や機器の持ち出しを禁止する
業務で使用するPC・USBメモリなどの機器や情報は、原則として社外への持ち出しや私物端末の社内ネットワーク接続を禁止します。
やむを得ず持ち出す場合は、端末の暗号化やパスワードロックを施したうえで、事前承認制とするルールを整備しましょう。これにより、外部環境での紛失・盗難リスクを最小化できます。
また、ログインIDやパスワードを第三者に伝えたり、メモに書いて可視化された状態で放置する行為は避けなければなりません。
SNS投稿や公共の場での会話など、業務で知り得た機密情報を漏らす可能性のある行為も社内ルールで禁止し、徹底させましょう。
信頼性の低いサイトやメールは開かない
コンピューターウイルスやスパイウェアなどにより、自社のデバイスに被害を与えられてしまうケースもあります。添付ファイルやURLをクリックしただけで感染するケースがあるため、身に覚えのないメールは開かない、怪しいリンクは踏まないといった基本行動を全従業員に周知しましょう。
正規サイトを装った偽サイトも増えているため、URLが正規ドメインかどうかの確認も徹底が必要です。万が一クリックしてしまった場合は、ネットワークから切断したうえ、IT管理部への連絡、さらにパスワードの変更とすばやい対策を実施しましょう。
また、重要なファイルやデータは定期的にバックアップをとっておき、万が一の際に備えることも大切です。「今まで被害にあっていないから大丈夫」だと油断せずに、徹底した対策をとりましょう。
情報漏洩の対策ツールと導入する
情報漏えいは、従業員の不注意や操作ミスといった「人的要因」によって発生するケースが非常に多く見られます。しかし、どれだけ社内教育を徹底しても、人間が関与する以上、ヒューマンエラーを完全に排除することは困難です。
そこで有効となるのが、データ漏えい防止ツールなどの情報漏えい対策システムの導入です。
これは、社内ネットワーク上を流れるデータや端末上のファイル操作を常時監視し、機密情報の不正持ち出しや不審な通信をリアルタイムで検知・遮断します。たとえば、社外への無断メール送信やクラウドストレージへのアップロード、USBメモリへのコピーなどが検知された場合、即座に警告を出したり、自動的に操作をブロックしたりできます。
さらに、こうしたツールにはログの一元管理機能やアクセス権限の自動制御といった機能も搭載されているため、管理者は手作業による監視業務を大幅に削減できます。結果として、情報漏えいを未然に防ぐ確率を高めるとともに、管理者側の負担軽減と内部統制の強化を同時に実現できるのです。
ツール導入にあたっては、取り扱う情報の機密レベルや従業員の業務形態(リモートワークの有無など)を考慮し、自社のリスクに最適化された機能を持つ製品を選定することが重要です。
まとめ
情報漏えいを防ぐためには、「情報や機器の持ち出し制限」「不審なメール・サイトを開かない習慣づけ」「バックアップ体制の確立」といった基本対策を徹底することが第一歩です。加えて、DLP(データ漏えい防止)ツールなどのシステムを導入することで、人為的なミスや不正をリアルタイムに検知・遮断でき、リスクを大幅に低減できます。
重要なのは「ルール・教育・技術」の三位一体で対策を講じることです。「今まで被害がなかったから大丈夫」という油断を捨て、自社に合った情報セキュリティ対策を早期に整備し、顧客と企業双方の信頼を守っていきましょう。